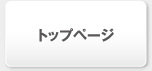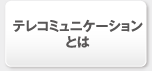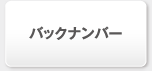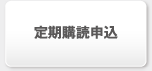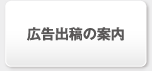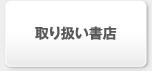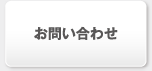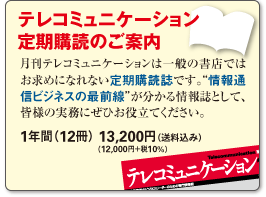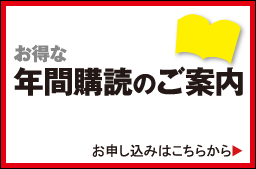Interviewインタビュー
2016年1月号
IoT時代の新ネットワークを構築
B2B2Xモデルへの転換を支える

小林充佳氏
(こばやし・みつよし)
1980年3月慶應義塾大学工学部電気工学科卒業。82年3月慶應義塾大学大学院電気工学専攻修士課程修了。同年4月日本電信電話公社入社。2002年5月西日本電信電話人事部担当部長。06年6月同岡山支店長。08年7月同サービスマネジメント部長。10年6月同取締役サービスマネジメント部長。12年6月日本電信電話取締役技術企画部門長・新ビジネス推進室長兼務。同年6月エヌ・ティ・ティ・コムウェア取締役(現職)。14年6月日本電信電話常務取締役技術企画部門長(現職)
NTT
常務取締役 技術企画部門長
小林充佳 氏
NTTは、B2CモデルからB2B2Xモデルへの移行を進めている。市場環境が大きく変化するなかIoT時代に向けたコンセプトとして「コラボレーション・プラットフォーム」を打ち出した。その中核を担う新しいネットワーク構想が「Netrosphere」だ。小林充佳常務は「顧客最適のサービスを提供したい」と抱負を語る。
●NTTグループは持株の鵜浦博夫社長の下、“プロバイダー”から“バリューパートナー”へと歴史的な大転換を図っています。新たなステージへ向けた取り組みには「ネットワークサービスの収益力強化」も打ち出されていますが、どういう状況でしょうか。
小林 2020年の東京オリンピック・パラリンピックや地方創生を契機に、ネットワークや通信回線をベースとした従来のB2Cモデルから、我々が「触媒」となって多様なプレイヤーにネットワークなどサービスを提供するB2B2Xモデルへと大きく舵を切ろうとしています。
その際、エンドユーザーに選ばれることはもちろんですが、「ミドルB」(B2B2Xの真ん中のB)のサービス事業者に「NTTと組んでみよう」「NTTと一緒にビジネスを展開したい」と考えていただけるような存在になることが必要です。
そのためには、高速かつ大容量で安価なネットワークを提供するだけでは十分ではありません。そこで2015年5月に発表した「新たなステージをめざして2.0」の中で、持続的な成長に向けた取り組みの1つとして「コラボレーション・プラットフォームの強化」を盛り込みました。
●コラボレーション・プラットフォームとは、どのような概念ですか。
小林 我々は、「シームレスサービス・プラットフォーム」「セキュリティオペレーション・プラットフォーム」「ビッグデータアナリシス・プラットフォーム」という3つのプラットフォームの総称をコラボレーション・プラットフォームと呼んでいます。
NTTグループの強みは高品質なネットワークやアプリケーション、販売チャネルですが、それらを単体で持っているだけでなく、+αの付加価値も提供できることをコラボレーション・プラットフォームを通じてアピールしていこうとしています。
オーケストレートする役割
●各プラットフォームはそれぞれどのような役割を担うのですか。
小林 まずシームレスサービス・プラットフォームは、製造・金融・流通などさまざまな産業分野で、サービス事業者(グループ内のNTTドコモやNTTデータを含む)に対して、我々が提供できるICTサービスや機能ラインナップを総称して呼んでいます。
具体的にはネットワークやクラウド、その上に載っているさまざまなサービスを提供します。ポイントは、自社サービスだけでなく顧客の要望があれば他社サービスも含めてアグリゲートし、顧客最適のシームレスサービスを提供できるところです。
例えばクラウドサービスは、すでにアマゾンの「AWS」やマイクロソフトの「Azure」を使われているお客様が数多くいます。NTTコミュニケーションズ(以下、NTTコム)では自社のクラウドサービスのユーザーが、AWSやAzureを利用するシステムも含めてハイブリッドに利用できるICT環境を構築していますが、こうしたマルチクラウドはもはや当たり前になっています。
IoT(Internet of Things)だとなおさらで、すべてのデバイスがNTTの回線につながっているという状態は現実的ではありません。
そうした中で、お客様の要望があれば競合相手のサービスも組み合わせ、全体を「オーケストレート」する役割を我々が担っていこうというのが、シームレスサービス・プラットフォームの基本コンセプトです。
司令塔としての役割を担うマルチオーケストレータがキーになりますが、他社サービスとのAPIを規定しうまくコントロールすることで、ユーザー最適のシステムを提供できるようにしたいと思います。これがB2B2Xモデルの基盤となります。
●NTTの持つ強みを従来のネットワークよりもっと上位のマルチオーケストレータで発揮するということですね。
(聞き手・土谷宜弘)
続きは本誌をご覧下さい