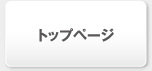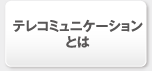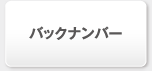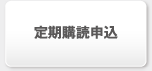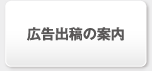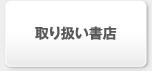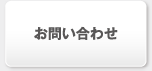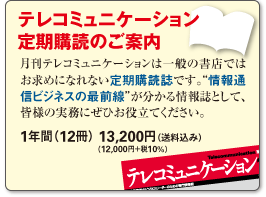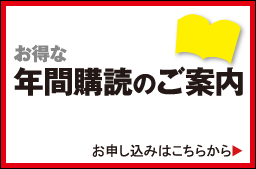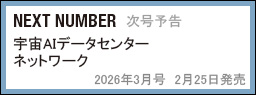Interviewインタビュー
2023年7月号
O-RANへのシフトは不可避
5000億円をIOWNの世界へ

木内道男 氏
(きうち・みちお)
1989年NEC入社。電子交換機のソフトウェア開発やルーター開発に従事し、2015年に日本電気通信システムに出向、共通プラットフォーム開発の責任者。2016年にNECに復帰し、キャリアサービス事業部にてNFVの開発をリードし、通信事業者向け仮想化モバイルコアネットワークソリューションを世界で初めて展開(発売)。2019年にモバイルコアのソフトウェア、OSS/BSS開発を統括し、2021年に執行役員としてネットワークインフラ事業全体をリード。2023年にCorporate EVP 兼 テレコムサービスビジネスユニット長に就任
NEC
Corporate EVP 兼
テレコムサービスビジネスユニット長
木内道男 氏
NECが組織改革を行い、通信事業者向けビジネスを担う「テレコムサービスビジネスユニット(BU)」のBU長に木内道男氏が就任した。O-RANをはじめとする5GビジネスやIOWNなどに、NECはどう取り組むのか。NECのテレコム事業をリードする木内氏に、現状と今後の見通し、そして成長戦略を聞いた。
●今年4月1日付の組織改革で、通信事業者向け事業を担う「ネットワークサービスビジネスユニット(BU)」が「テレコムサービスBU」へ改称されました。
木内 ご存じの通り、国内の通信事業者の業績は過去最高益といった状況にありますが、「官製値下げ」の影響もあって、ARPUやネットワーク領域の設備投資は減ってきています。そうしたなか、我々のBUは今まで「ネットワーク領域にフォーカスします」という名称でした。
しかし今後は、ネットワーク領域だけではなく、通信事業者の成長全体に対して、きちんと貢献できるようにと「テレコムサービス」へと名称を変更しました。
ネットワークは、国の重要インフラであり、安全保障の問題もあります。国内最大の通信ベンダーとして、ネットワークに関する責任をしっかりと果たしながら、非通信領域でも事業を伸ばしていくことが大切だと考えています。
●所管する事業自体も少し変わりましたね。
木内 LAN製品やローカル5Gといったエンタープライズ向けのアセットは、全社横断でDXに必要な製品・サービスを提供する「デジタルプラットフォームBU」へ移しました。
また、従来からグローバル5G事業は我々のBUでしたが、これまでグローバル担当のBUが所管していた海底通信ケーブル事業、先頃カーブアウトを発表したパソリンクの事業についても、テレコムサービスBUに戻しています。
NECはアクセルを踏み過ぎた
●投資抑制が続く国内だけではなく、グローバルで見ても5Gによるイノベーションは期待通りには進んでいないのが現状です。
木内 海外ベンダーと比較すると、国内でNECは健闘していると思っています。しかし、まだ本格的には5G時代のネットワークになっていませんし、そうなっていないからこそ、5Gの特性を活かしたサービスもなかなか出てこない状態に陥っています。通信事業者は、今後の通信収入の伸びについて厳しく見ており、通信収入の状況を見極めてバランスをとりながら設備投資を行っている状況と理解しています。
3G/4Gと比較した5Gの特徴の1つは、既存設備を活用できてしまうことです。4G設備を用いるノンスタンドアロン(NSA)方式で良くなるのはスループットだけで、レイテンシーなどは改善されません。ですから、スタンドアロン(SA)方式が「リアルな5G」だと思っていますが、NSAでエリアカバーしても「5Gです」と言うことができます。
5Gには2種類あって、まだ本当の意味での5Gにはなっていないのです。法人向けなど、本当の5Gで広がる新しい用途は、通信事業者にとっても成長機会の1つですし、そこに一緒に取り組んでいくことが、我々が5Gで事業を伸ばしていく1つの方法だと思っています。
●O-RAN(Open Radio Access Network)の商用導入の本格化もこれからです。
木内 O-RANの1つの利点は、汎用サーバーに基地局ソフトウェアを搭載して仮想化することで、自動運用が可能になることです。しかしその一方、O-RAN準拠のRANシステムは、専用ハードウェアのRANシステムと比べて、現状では消費電力が高いというデメリットがあります。最近のエネルギー価格高騰によって、このO-RANのネガティブな面が大きくなってしまいました。加えて、昨年度は景況感もあまり良くなく、新しいテクノロジーにチャレンジするお客様自体が減りました。O-RANの導入は現在、ほぼグリーンフィールドに限られ、ブラウンフィールドでの導入は進んでいません。
ところが、そうした状況にもかかわらず、NECはアクセルを踏み過ぎてしまったところがあって、その反省から今、海外でもしっかり利益が出せるようにと、収益性改善のための構造改革を進めているところです。具体的には海外の人員体制の見直しや、収益性の観点でのフォーカス案件の選択に取り組んでいます。
●O-RANの導入はいつ頃、本格化しそうですか。
(聞き手・太田智晴)
続きは本誌をご覧下さい