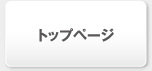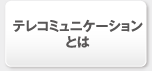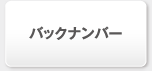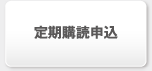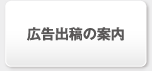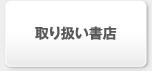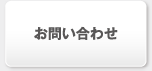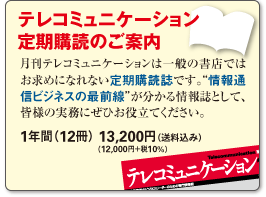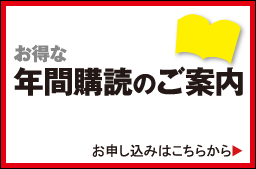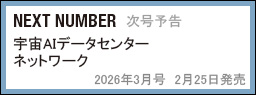Interviewインタビュー
2025年2月号
5Gは「AIやロボットのため」
vRAN前提に自動化・DX化

木内道男 氏
(きうち・みちお)
1966年2月生まれ。1989年NEC入社。電子交換機のソフトウェア開発やルーター開発に従事し、2015年に日本電気通信システムに出向、共通プラットフォーム開発の責任者。2016年にNECに復帰し、NFVの開発をリードし、通信事業者向け仮想化モバイルコアネットワークソリューションを世界で初めて展開(発売)。2019年にモバイルコアのソフトウェア、OSS/BSS開発を統括し、2021年に執行役員としてネットワークインフラ事業全体をリード。2023年にCorporate EVP 兼 テレコムサービスビジネスユニット長に就任
NEC
執行役 Corporate EVP 兼
テレコムサービスビジネスユニット長
木内道男 氏
NECが通信事業者向けビジネスの「ソフトウェアシフト」を進めている。vRANやOSS/BSSなどを土台に通信事業者の自動化・DX化に貢献し、「規模の経済」とは距離を置いた、高付加価値ビジネスへ転換するのが狙いだ。テレコムサービスビジネスユニット長を務める木内氏に、事業戦略や5Gの今後などを聞いた。
●NECの通信事業者向けビジネスを担うテレコムサービスビジネスユニットはここ最近、グローバル5G事業の見直しや、ハードウェアからソフトウェアへのシフトに取り組んできました。こうした構造改革の結果、2023〜2025年度の調整後営業利益の年間平均成長率(CAGR)は37.5%の見込みと、収益性が大きく改善しています。
木内 ソフトウェアシフトを進めてきた理由は大きく2つあります。
1つは、必ずしも専用機を作らなくても、汎用サーバーでいい領域がどんどん増えてきていることです。基地局も、DUやCUといった親局側の装置は、技術的には専用機が必要なくなってきています。
専用のハードウェアを作るとなると「規模の経済」になりますから、我々のマーケットでのポジションを考えても、そうした方向へシフトした方がビジネスはやりやすいです。対して、既存の主要ベンダーの場合、ハードウェア部分の売上を失うようなビジネスモデルはやりたがりません。
2つめは、ソフトウェア化しないと自動化も進展しないことです。
日本の通信事業者のオペレーション担当の方は定着率もスキルも高いので、国内ではあまり問題になってきませんでしたが、従業員の流動性が高い海外では「3年で全員変わる」みたいな話もあります。そのため、人間が頑張るというより、システムに業務をインプリしていく方向性になっています。労働人口が減少していく中、日本もそうした形へシフトしていく必要がありますが、ソフトウェア化して自動制御できる範囲を広げていくことが重要です。
例えば、基地局の購入費用と建設工事費用は同じくらいだと思いますが、CU/DUなどをソフトウェア化して自動でデプロイできれば、基地局開設までのスピードは速くなり、建設工事費用も下げられます。
RUは製造中心のベンダーと
●グローバル5G事業については、オープンRANの潮流に乗って、海外での基地局シェアを拡大させる戦略でした。しかし、オープンRAN市場の立ち上がりの遅れの影響を受け、投資の抑制などの見直しを行いました。その裏返しとして、ソフトウェアシフトを図っている面もあるのですか。
木内 NECは元々、ソフトウェアベースのオープンRAN、vRANでやっていく戦略です。グローバル5G事業の見直しとソフトウェアシフトは直接リンクしているわけではありません。
グローバル5G事業を見直したのは、他の大手ベンダーのように、各国に拠点を置いてデリバリーする体制を作ったものの、5Gのマーケットが伸びない中、費用だけが先に出て行く形になってしまったからです。また、せっかくソフトウェア中心のソリューションにしているにもかかわらず、ハードウェアのデリバリーを前提にしたような体制でもありました。そこでグローバル5G関連の投資を見直し、海外の体制についてもNTTドコモと立ち上げた合弁会社「OREX SAI」などに集約する形に見直しました。
グローバル5G事業の黒字化は、元々の計画から1年前倒しの2024年度に達成できる見通しです。
●グローバル5G事業の見直しとソフトウェアシフトに伴い、気になるのは、RUをはじめとするハードウェア事業の今後です。
木内 RUは専用ハードウェアが必要ですから、当然、専用ハードウェアでやっていきます。誤解を生みやすいかもしれませんが、汎用的なハードウェアに載せられるものに限って、ソフトウェアに絞ってやっていくことを我々は「ソフトウェアシフト」と表現しています。
●「規模の経済」が大きく働くマーケットでの戦いも続けるということですか。
木内 国内で使うものについては、自分たちで完成品まで手掛ける可能性が高いですが、基本的にはマニュファクチャリング(製造)中心のベンダーと組んでいく考えです。
例えばRU関係では、ビームフォーミングはマニュファクチャリング中心の会社だけでは作れません。こうした最先端の領域について、ソフトウェアをライセンス販売したり、図面や設計ノウハウなどを提供することで、現地のベンダーが自社生産できるようにします。
すでにアジアのあるベンダーとはいろいろ組んでいますし、今、他のベンダーとも議論しています。自国の産業として立ち上げたい国、そのために関税をかけている国など、今後さらにいろいろな地域のベンダーとのパートナーシップが出てくると思っています。
●NECは高い技術力を提供し、完成品の製造・デリバリーは現地のベンダーが行うというモデルですね。
(聞き手・太田智晴)
続きは本誌をご覧下さい